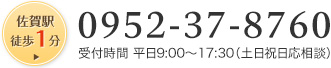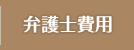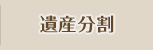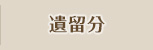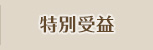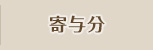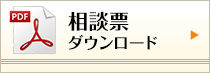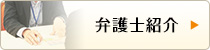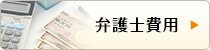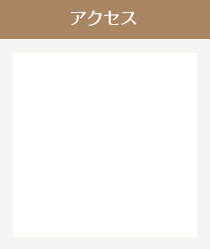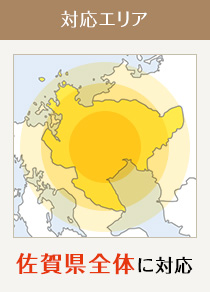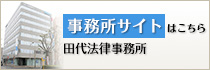- HOME
- 相続の手続きについて
- 遺留分請求の期限はありますか?
Q3.遺留分請求の期限はありますか?
|
遺留分請求には、期限があります。
具体的には、相続の開始と遺留分減殺の対象になる遺贈や贈与があったことを知ってから1年以内に遺留分減殺請求をしないと、請求ができなくなってしまいます。 上記の事実を知らない場合でも、相続が開始してから10年が経過すると、やはり遺留分請求はできなくなります(民法1042条)。 |
 |
遺留分が認められる場合、放っておいても遺留分の返還を受けることはできないので、受遺者(遺贈を受けた人)や受贈者(贈与を受けた人)に対して、遺留分減殺請求をしなければなりません。
この遺留分減殺請求については、民法によって期限が定められています。1つ目は消滅時効です。遺留分減殺請求権については、以下の2つの事実を知ってから1年以内に行使しないと、時効によって消滅してしまうので、その後はどのような手段を使っても相手に遺留分を請求することができなくなります。
①相続があったこと
②遺留分減殺の対象になる贈与や遺贈があったこと
この遺留分減殺請求については、民法によって期限が定められています。1つ目は消滅時効です。遺留分減殺請求権については、以下の2つの事実を知ってから1年以内に行使しないと、時効によって消滅してしまうので、その後はどのような手段を使っても相手に遺留分を請求することができなくなります。
①相続があったこと
②遺留分減殺の対象になる贈与や遺贈があったこと
また、これらの事実を知らなかった場合にも、除斥期間が問題になります。除斥期間とは、①や②の事実を知らなくても、相続開始後10年が経過すると、当然に遺留分減殺請求ができなくなってしまうことです。
遺留分減殺請求をする場合、これらの期間制限があるので、相続が起こったことや遺言や遺贈があったことを知ったら、早めに遺留分減殺請求の手続きをすることが大切です。
相続に関するQ&A
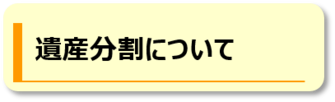 |
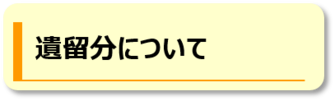 |
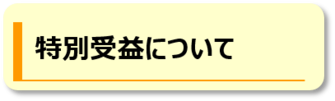 |
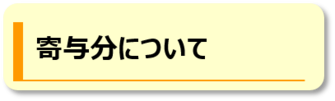 |
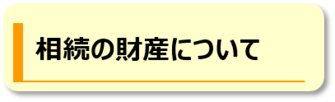 |
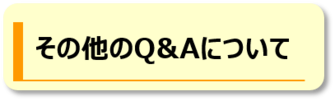 |
遺産分割についてのQ&A
 |
●Q1.遺産分割とはどのようにするのですか? ●Q2.遺産分割の手続きの方法を教えて下さい。 ●Q3.遺産分割したあとに遺言がでてきたらどうなりますか? |
遺留分Q&A
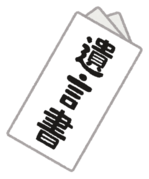 |
 |
|
寄与分Q&A
 |
 |
|
特別受益Q&A
 |
相続の財産についてのQ&A
|
●Q1.遺言で父から財産の全てを相続しました。しかし、他の兄弟から遺留分の請求をされました。どうしたらいいですか?相続税や葬儀費用も差し引くことはできますか? ●Q2.これまで両親と同居し、両親の面倒をみてきました。遺産を多めにもらいたいのですが、他の兄弟は法定相続分による分割を主張しています。何か多めにもらう方法はないでしょうか? |
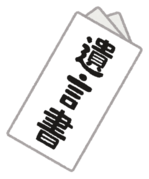 |
 |
その他相続Q&A
|
●Q1.遺産(全相続財産)を調査する方法はありますか? ●Q2.法定相続人、代襲相続人とは? |
 |
些細なことでもまずはお気軽にご相談ください
| ●HOME | ●事務所紹介 | ●弁護士紹介 |
| ●弁護士費用 | ●ご相談の流れ | ●アクセスマップ |

〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央1-10-37 佐賀駅前センタービル5階
田代法律事務所 弁護士 田代祐誠(佐賀県弁護士会所属)
田代法律事務所 弁護士 田代祐誠(佐賀県弁護士会所属)
Copyright (C) 田代法律事務所 All Rights Reserved.