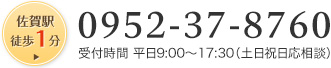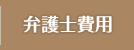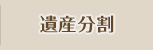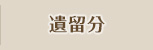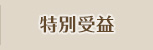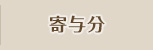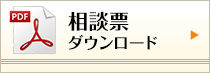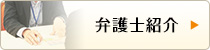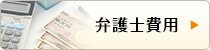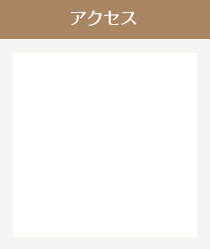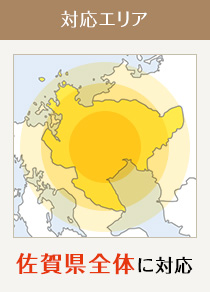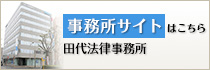- HOME
- 相続人が預金を使い込んでいる場合
- 預貯金の使い込み、使途不明金問題で返還請求された場合の対処方法
預貯金の使い込み、使途不明金問題で返還請求された場合の対処方法
| 預貯金の使い込みや使途不明金が発覚すると、相続人間では大きな問題になります。この場合、はっきりした証拠が残っていないこともあり、被相続人自身が出金しているケースも多いので、どこからが使いこみなのかが明らかになりにくいです。 |
 |
特に、自分が被相続人の預貯金を管理していて、使いこみをしたと主張されたら、放っておくと裁判を起こされるケースなどもあるので大変です。
今回は、預貯金の使いこみをしたと言われて責任追及された場合の対処方法について、解説します。
1.相手から請求書が届いたらどうする?
自分が被相続人と同居しており、預貯金や家計の管理をしていた場合、どうしても生活のために被相続人の預貯金を使いますし、被相続人の財産と自分の財産が混同してしまいがちです。そういったケースでは、相続開始後、ある日突然他の相続人から「預貯金の使いこみをしている。返せ」と言われることがあります。
相手から口頭で通知されることもありますが、「内容証明郵便」という郵便で通知書が送られてくることもありますし、弁護士から請求書が届くこともあります。
このようなとき、慌てふためいて適当な言い訳をしてはいけません。
たとえば「それは~に使った」などとうろ覚えの回答をして、後で考えてみたら違った、ということもありますが、後で異なる説明をすると、相手からは「ごまかしている→やはり嘘をついている、使い込んだに違いない」ということになってしまうからです。
そこで、請求を受けたら、いったん回答は保留にして、まずは弁護士に相談をしましょう。
そして、後から撤回することのないよう、よく思い出してから、確実な内容の回答をすべきです。
2.相手に対する返答の方法は?
それでは、相手に返答をするとき、具体的にはどのような内容の回答をしたら良いのでしょうか?自分としては「1円も返したくない」というのが本当のところでしょうけれど、それは正しい対応なのかが問題です。
まず、被相続人の存命中に定期的に少額の出金をしている場合などでは、被相続人の生活費に使ったと認められる可能性が高いです。
また、被相続人の生前、本人が元気なときに20万円や30万円などの出金が1,2回あっただけのケースなどでも、被相続人の意思に基づく出金と認められる可能性が高いと言えます。
これに対し、被相続人が体調を崩した後、多額の出金をしている場合などでは状況が異なります。被相続人のために預金を下ろしたというのであれば、何に使ったのかの説明が必要ですし、使途についての領収証がないと相手は納得しないでしょう。
被相続人に頼まれて下ろしたと言っても、やはり何の証拠もないと苦しくなりますし、被相続人から贈与されたと言っても、贈与契約書がないなら「証拠がない」と言われます。
被相続人自身がしたのではないと考えられる多額の出金がある場合、なにがしかの返金をすることによって早期に話し合いで解決するのがベストな方法になります。
このように、使いこみを疑われた場合、初動からの対処の仕方が非常に重要です。自分では適切な判断ができない場合、早めに弁護士に相談しましょう。
些細なことでもまずはお気軽にご相談ください
| ●HOME | ●事務所紹介 | ●弁護士紹介 |
| ●弁護士費用 | ●ご相談の流れ | ●アクセスマップ |

〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央1-10-37 佐賀駅前センタービル5階
田代法律事務所 弁護士 田代祐誠(佐賀県弁護士会所属)
田代法律事務所 弁護士 田代祐誠(佐賀県弁護士会所属)
Copyright (C) 田代法律事務所 All Rights Reserved.