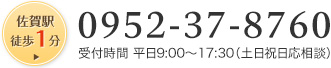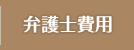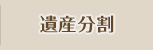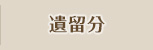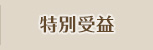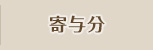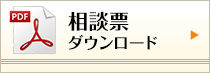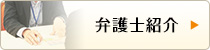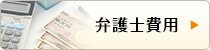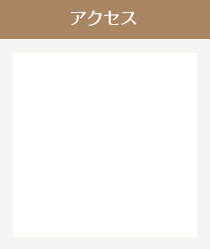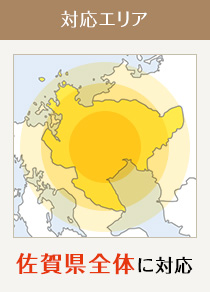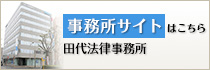寄与分が問題になる場合
 |
寄与分とは、相続人の中で、被相続人の維持・増加に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。 |
寄与分の例
例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝って、被相続人の財産形成に2000万円の寄与があった場合、
見なし遺産=遺産:1億円-2000万円(兄の寄与分)= 8000万円
兄の相続分:8000万円 × 1/2 + 2000万円 = 6000万円
弟の相続分:8000万円 × 1/2 = 4000万円
となります。
寄与分の代表的な態様としては、次のようなものがあります。
① 被相続人である親の家業に従事して、財産を増やした(家業従事型)② 親の事業に関して資金援助した(金銭出資型)
③ 病気になった親の療養介護に従事した(療養看護型)
④ 親を扶養して生活の面倒を見ていたため、親が支出を免れた(扶養型)
⑤ 親の不動産の賃貸管理や立退き交渉などを行った(財産管理型)
いずれの場合においても、親子の関係に基づいて期待されるようた程度を越える貢献が必要であり、多くの場合、無償性や継続性、専従制が求められます。
寄与分を主張できる人
寄与分の主張ができるのは、法定相続人に限られます。
特別受益と寄与分でお悩みの方はこちらもご覧下さい
| ●特別受益と寄与分 | ●特別受益が問題になる場合 | ●寄与分が問題になる場合 |
些細なことでもまずはお気軽にご相談ください
| ●HOME | ●事務所紹介 | ●弁護士紹介 |
| ●弁護士費用 | ●ご相談の流れ | ●アクセスマップ |

〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央1-10-37 佐賀駅前センタービル5階
田代法律事務所 弁護士 田代祐誠(佐賀県弁護士会所属)
田代法律事務所 弁護士 田代祐誠(佐賀県弁護士会所属)
Copyright (C) 田代法律事務所 All Rights Reserved.